|
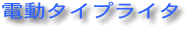
|
|
その後、昭和55、6年ごろ (1980~81) に、電動タイプライタなるものを手にした。
(ドイツの)オリンピアの製品だった。
この電動タイプライタは高価なもので、当時20万円ぐらいした。
|
当時、ことのはずみで、ドイツ人教師 W氏と同居(?研究室を共有)していた。
このW氏は前橋に二年ほど滞在したのち帰国した。
オリンピアの電動タイプライタは、W氏が研究費で購入したものを、
氏が帰国してから、ちゃっかり使わせてもらったわけである。 |
|
これはドイツ語専用のタイプライタで、ä, ö, ü, ß を打つのに、二度打ちをする必要はなかった。
ä, ö は2段目右に並んでいて、ü は3段目右端にあって、ß は1段目右だったか(?)。
かの電動タイプライタは、もう手許にないので、確かめようがない。
4、5年前に、不要物品として、廃棄処分にしてしまった。
ともかく、右の小指で、わりと打ちやすいところにあった。
|
また、y と z は、一般のタイプライタでは、
(いまの時代なら、一般的なパソコンのキーボードでは、と言うべきか)
ご承知のように、一方は動かしやすい右手人さし指で打てるところに、
もう一方は、やや使いにくい左手小指で打つところにあるが、
これは、まちがいなく英語圏のひとの都合でそうなっているのであろう。
|
ただし、これだと、ドイツ語を打つ場合には、少々、効率が悪い。
そのことを考えた上でのことか、このドイツ語用電動タイプライタは、
この y と z の位置が、一般の英文用タイプライタとは、逆になっていた。
|
つまり、ドイツ語としては、めったに利用しない y のキーの位置に、
頻度の高い z が置かれていて、ドイツ語を打つには、かなり便利に出来ていた。 |
|
しかも、この電動タイプライタは、タイプライタとしては画期的なものであった(そう思われた)。
|
今までの手動のタイプライタは、キーを叩くと、
それに応じて、ハンマーが起き上がって、紙面をひっぱたいた。
しかもその印字の濃淡は、ひとがタイプを叩く、その指の圧力に完全に比例するものだから、
この手動のタイプライタを使うと、個々人の技量の差が、歴然と現れた。
|
しかし、この新型の電動タイプライタの印字装置は、
ハンマー型とは大きく異なり、コアと呼ばれる、金属製で球形の、
その表面に、活字がびっしりと並んだものだった。
|
このコアが、キーを軽くたたいた、その瞬間に、
それこそ何分の一秒くらいのタイムラグで、
上下左右にすばやく回転して、目当ての文字をカシャッと印刷した。
しかも濃度は均一であった。 |

|
|
|
だから、仕上がりは、だれが打っても、同じように、じつにきれいで、
正式の書類を作成するのには、とても重宝した。
|
強いて難点を挙げれば、タイプミスに、あとあとになって気がついた場合の訂正は、
やはり、難しい、というか、不可能だった、ことである。
|
もちろん、タイプ中の紙を、まだ抜き取らないうちに、自分のタイプミスに気がつけば、
訂正したい文字を、消去リボンを利用して( s を直したいなら s と)もういちど打ち、
ついで、印字用リボンで、その場所に他の新たな文字を打つことで、
見苦しくないかたちに、訂正することができる。
|
しかし、もう十分と思って、紙をキャリッジから抜いたら最後、
そしてそうしてから、間違いに気がついても、時はすでに遅し、である。
少なくとも、公式書類として提出できるようなものには、直らない。
|
|
小生と同僚のTは、いちど、共同で、外国人教師 W氏への招聘状を打ったことがあった。
Tは、機械ものに疎いかれにしては珍しく、新登場の電動タイプライタを、
この時には、すでに購入していた。アードラーの製品だった、と思う。
|
この新型の機械を、小生の研究室に持ち込んで、
(ひとりで公式書類を打つのは、精神的にとても疲れるので、)
二人で、ときどき交代をしながら、A4判の用紙にびっしりと詰めて打った。
|
そして、その一枚がほとんど終わりまでいったとき、改めて上の行にも目を通して、
これでよし、と思って、引き抜いた。
|
ほとんどその瞬間に、その最後の行あたりに、致命的な間違いを発見し、
泣く泣く、もういっぺん、頭からやり直したことを、いまでもよく憶えている。
|
|
|
|
|
|