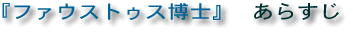
|
|
 |
左: バイエルン州南部地域の農家
『ファウストゥス博士』の中で
「農家シュヴァイゲシュティル」として描かれている
Photographie links:
Hof Schweighardt, Polling/Obb.-
<Hof Schweikgestill,Pfeifffering>
im <<Doktor Faustus>>
aus:
Klaus Schröter: Thomas Mann.
rowohlts monographien Nr.93.
Rowohlt Taschenbuch Vlg., Reinbek bei Hamburg, 1964
|
|
『ファウストウス博士』においては、現実の社会の変化、すなわちドイツの悲劇的運命が、
語り手を介して、一昔楽家の生涯に象徴的に重ね合わされている。
つまり、ドイツの作曲家アードリアーン・レーヴァーキューンとその祖国ドイツはどちらも、
窮地を打開するために、悪魔と契約を結び、そしてまさにそれ故に悲惨な最期を遂げざるをえないと
一 これは外見上のことであるが 一 描かれている。
作者は、このような破滅がある程度ドイツ人の本質に由来していると見た。
しかしもちろんドイツの悲劇はあくまで社会的背景であり、
作者の主眼はドイツ人の代表としての一個人である音楽家
アードリアーン・レーヴァーキューンの生涯におかれている。
作者はその際、すでに述べたように、主にフリードリヒ・ニーチエの悲劇の生涯をモデルにし、
その運命の主要な部分に意識的に主人公の運命を符合させた。
しかしながら、両者の運命が現象としては非常に類似しているにもかかわらず、
その本質は 一 創作であれば当然のことかもしれないが 一 心ずしも一致してはいない。
1885年、いわゆるルター地方のある富裕な農家に生まれた主人公アードリアーン・レーヴァーキューンは、
子供の頃から際立った才能の持ち主であることを十分にうかがわせていた。
かれは近くのカイザースアッシエルンのギュムナージウムに入学すると、
その町で楽器商を営んでいる叔父のもとから通うことになる。
その頃、こっそりと独学で和声法などを調べていたが、
あるとき小さなオルガンを弾いているところを叔父に見つかり、
クレッチュマルというドイツ系アメリカ人のオルガン奏者の個人教授を受けるようになる。
かれはギュムナージウムの最上級生になるとへブライ語の勉強を始め、ハレ大学神学部に進む。 |
初めてこの町に来たアードリアーンが荷物を下宿において町に出、ひとりの男に案内を乞うと、
途中で感違いをされて、娼家に連れ込まれてしまう。
驚いたアードリアーンは目前にあったピアノに救いを求め、二三度和音を鳴らしてから表に飛び出す。
だが、アードリアーンが弾いているとき、ひとりの女が、腕でかれの頬をさすったのである。
語り手ゼレーヌス・ツァイトブロームの解釈によれば、
「高慢な精神が、魂のない衝動との遭遇という外傷を負った。」という。
アードリアーンは、このほぽ一年後、
今度は自分の意志で同じ場所を訪ねるが、女はもうそこにはいない。
かれは女が移った先を確かめ、1906年5月、
グラーツでリヒャルト・シュトラウスの『サロメ』のオーストリア初演を聞くことを口実に、
ハンガリーのプレスブルク[ポジョニィ]へと足を伸ばし、女に再会する。
ここまで旅をしてきたのは彼女のためであった。
それを聞いた女は、自分の身体には触れないようにと警告をする。
それにもかかわらずアードリアーンは女と関係をもつ。
アードリアーンはおそらくこのとき初めて、女が病気であることを知った。
従って、たとえ心の隅に以前から神に対する挑撥、デモーニッシュな受胎への欲求があったとしても、
最初からそれを求めてプレスブルクヘ来たわけではない。
ただ、きわめて宗教的な人間であるとともに、鋭敏な感覚と才知を備えたこの男は、
警告を聞いた瞬間、直観的に自分のおかれた運命を察知し、
病気による精神の超躍を心中ひそかに期待して、ひとつの賭を行なったのであろうか。
数週間後、アードリアーンは局所罹患のため、住所録を繰って医者を探し、その治療を受ける。
しかし最初に訪ねた医者は急死し、二人目の医者は官憲に逮捕される。
するとそれ以後、アードリアーンは治療を受けるのをやめてしまう。
ツァイトブロームは意味ありげに、「かれはいわば脅かされた」と述べている。
1910年、アードリアーンはミュンヒェンヘ移り、
ランベルク通りの市参事会員未亡人ロッテ夫人の家に間借りをする。
そして6月末に若い作家兼翻訳家のリューディガー・シルトクナップと二人でイタリアヘ赴き、
サビーニ山中のパレストリーナに住みつき、ほとんど作曲に没頭して、二年間を過ごすことになる。 |
この滞在中のある夏の日の夕方、ひとり長椅子に坐り、読書をしていると、
悪魔が現れて、アードリアーンと話を交わすのである。
眼が覚めてからこの対話を楽譜用紙に書きつけたアードリアーンが
この現象を信じていたか否かは判然としないが、
かれは病いによる精神の跳躍を期待していたゆえ、ある種の病気に罹れば、
普通の精神状態では知覚できないものを知覚するようになるかもしれないと思っていたことは確かである。
もちろん、病気が進行し、精神に異状を来し始めたころには、
悪魔の存在を本当に借じているような言動が目立つようになる。
ところで、アードリアーンの前に現れた悪魔の実体がたとえ何であれ、
ジューフィリスへの感染というかたちで現代的に血の契約を済ませていたとすれば、
悪魔はこの契約に従って、以後二十四年間、その期限が切れてアードリアーンの魂が悪魔の手に落ちるまで、
つまりかれが発狂するまで、いったいどのような働きをするのであろうか。
|
アードリアーンの幻想に現れた悪魔は、仕事に行き詰まっていたアードリアーンに対して、
今や作曲それ自体があまりにも困難になってしまっていること、
そしてそこからの脱出の道としてのパロディーという手段にも多くは期待できないこと、
従ってあとに残されているのは
「苦悩を、その現実の瞬間に、虚構や遊びをまじえず、ありのままに変容させずに表出することだけ」
であることを説く。
その後、アードリアーンはミュンヒェンの田舎で、管弦楽幻想曲などいくつかの作品を仕上げる。
しかし、次第に、アードリアーンの病気の症候が目立ってくる。
かれは烈しい頭痛と吐き気そして光に対する過敏な反応にひどく苦しむようになる。
発作は間敢的に幾度も繰り返されるが、その疲労困憊の中で、際立った作品が生まれる。
ひとつは、1919年の春、病気の重圧が一的に消滅した折りに、
かれの精神が、多幸症(オイフォリー)のように高揚し、完成したもので、
デューラーの15枚の版画を題材にした『木版画による黙示録』という作品である。 |
そして問題の作品、交響カンタータ「ファウストウス博士の嘆き」となる。アードリアーン・レーヴァーキューンがその生涯の最後にわずか一年と数カ月を要しただけで書き上げたこの作品は、魔術師の生涯と死を物語る古い民衆本を下敷きにしている。
1930年の5月、アードリアーンは、
完成したばかりのこの合唱交響曲を少しピアノで弾いて説明したいと、友人知己を招待する。
そして客人たちを前にして、悪魔と盟約を結びその助けを借りて作曲したこと、
友人を計画的に殺害したこと、自分の邪悪な視線で子供を殺してしまったことなどを告白し、
みずからを仮借なきまでに断罪し、あらゆる憐欄を拒わり、この世からの別れの挨拶をするのである。
|
アードリアーンは事情があって連れてこられた五歳になる甥のネポームクに、
アードリアーンにしては珍しく、そしておそらく生まれて初めて、すっかり心を奪われてしまった。
ところがこの子供は、来てニカ月後に脳膜炎に患り、その後わずか二週間のうちに死んでしまう。
アードリアーンはこの子供の死によって言い様がないほどの衝撃を受けた。
そして僅かの希望すら無残に打ち砕かれたアードリアーンのその苦悶の内面が、
最後に、烈しくほとばしり出て、かれ自身のすぐれた作曲技法を介し、芸術的に特異な作品へと生長する。
|
悪魔の化身、スピロヘータ・パリダがこの作品の成立に際して、
アードリアーンの感情を自由に発散させるのに与っていること、
また作品の内容そのものに対しても、その程度を限定することは不可能だが、
何らかの影響を及ぼしていることは言うまでもない。
しかしながら、肝心な点「悪魔との契約」という問題については、疑わしいと思われる。
悪魔は、アードリアーンの創作の主要な点、本質的な部分には、関与できなかったのではないか。
なぜならば、この作品の成立に関して何よりも大きな影響を及ぼしたのは「子供の死」であり、
作品の内容の主たるものはアードリアーンの生涯に亘る「苦悩」だからである。
このようにして生じた作品を悪魔によって産み出されたものとみなすわけにはゆかない。
このときのアードリアーンの話には明らかに精神錯乱のきざしが認められ、
かれが理性的な判断を十分にはできなくなっていることがうかがわれるが、それでもなお、
自分の生涯および完成した作品についての洞察、またその体験を通じて得た人間存在についての考察は、
筋の通った、しかもじつに鋭いものである。
伝記作者ゼレーヌス・ツァイトブロームの心は、主人公にたいする愛着と
そのデモーニッシュな面にたいする畏怖ないし猜疑とのあいだをしきりに揺れ動いている。
たしかにアードリアーンは、その高き目標に到達するためにはどんな犠牲も嫌わず、
またいかなる危険をもあえて冒す冷徹かつ傲慢な天才という面をもっていた。
そしてそこには宿命的な偶然の作用もあったけれども、
かれの心に痰しい期待が清んでいたことも事実である。
しかし、ひとりの人間としてのアードリアーン・レーヴァーキューンを、
先入見に捉われることなしに、観察してみれば、
この現代のファウスト博士の分裂した内面のもう一方を貫いている人間的感情が
一 そしてこの感情が、既に見たように、とくに最後の作品の成立に関して重要な役割を果たすのであるが 一
浮かび上がってくる。
たとえば、かれが妹の婚約者の人柄について、
「よい眼をしており、血筋がよく、正直で、欠点のない、清潔な人だ。
かれなら当然、妹に求婚してよい、妹をじっと見つめて、求めてもよい。」
と感想を述べるところ、
あるいは、
子供が危篤に陥ったとき、ツァイトブロームに対し、
「あの子供にたいして、このあいだのような、『おい、坊や、いつもおとなしく、云々』
といった言い方で話しかけるのはやめてくれ」と言う個所などは、
かれの「心の深奥」には、言いかえれば、アードリアーンという人間の「本質」には、
きわめて「人間的な感情」が潜んでることを示している。
アードリアーン自身は、「娼婦との抱擁」について、
芸術を救うために「悪魔との契約」という罪を犯したと「告白」をするけれども、
この女との一件を、改めて、別な角度から見てみると、つまり女の立場に身を置いてみれば、
かれの奥にひそむ人間的「感性」を、感じとることができる。
語り手も、
「遠方から旅をしてきた男が、あらゆる危険を冒して、彼女を断念することを拒んだということが、
この哀れな女を純化し、正当化し、高めながら、幸福にしたにちがいない。
そして彼女は、自分のためにかれがあえてしてくれたことに報いるために、
女性としてもっているすべての甘美さを尽したらしい」
と述解しているように、
アードリアーンの行為は、暗い衝動に促されているという一面があるのはじじつとしても、
その一方で、
病いに犯され、ブレスブルクヘと「吹き流され」おそらくきわめて惨めな境偶に追い込まれていた女に、
幾許かのものであれ、「生きる喜びを与えた」に違いない。
この「現代のファウスト」は、
たとえば、ゲーテによって描かれたような「古典的なファウスト」とは違った人間なのである。
ゲーテの、かの有名な作品においては、
いささか単純なところがあるが、心のすなおなグレートヒェンがファウストとの恋に溺れ、
そのために、この娘は、眠り薬の量を誤って、母を死なせ、嬰児を池に投じ、
死刑囚として牢獄に入れられ、ついには気が狂って果てる。
ファウストは、グレートヒェンの哀れな最期を、「かなりの程度」予測することができたはずである。
しかしかれは、おそらくはその「高速な理想のために」、やむなく娘を見捨てた。
アードリアーン・レーヴァーキューンはこのようなゲーテのファウストとは、
「倫理的観点」から見れば、「対蹠的な人間」と言える。
|
さて、招待した友人知己を前にして、この世からの「別れの挨拶」を済ませたレーヴァーキューンは、
ピアノに向かい、演奏に取りかかろうとする。その途端に、椅子から転げ落ちて、意識を失う。
意識は戻らないまま、そして肉体だけが生命を保ち、
アードリアーン・レーヴァーキューンは年老いた母親に伴われて、故郷へ帰る。
そのあとのレーヴァーキューンは、ただ生ける屍として、10年間を過ごし、
1940年8月25日に、この世から去る。 |
|
|
|
|
|