|

|
|
Thomas Mann stellt sich vor, daァ Charlotte Kestner durch das Wiedersehen mit ihrem Jugendfreund Goethe auf eine erlösende Versöhnung hoffte, aber mit dem Alten eine bittere Enttäuschung erlebte. Der Dichter Thomas Mann stellt in seinem Roman "Lotte in Weimar" Lottes Versuch dar, das Mißverständnis zwischen Lotte und Goethe, das durch die Publikation des Romans "Die Leiden des jungen Werthers" entstanden ist, zu lösen.
|
In dem Werdegang des Romans formt sich Charlottes Gedanke, der ihr am Anfang noch unklar war, allmählich durch die Gespräche mit den Goethe umstehenden Leuten, die innerlich unter dem Druck des großen Dichters stehen. Thomas Manns Goethe ist etwas karikiert, und, was die Menschlichkeit betrifft, so ist er als eine ziemlich problematische Person geschildert. Ihm gegenüber vertritt Lotte das Recht des normalen Bürgers. Goethes Erklärungen und Rechtfertigungen sind doch im allgemeinen zu abstrakt, deshalb ist es zweifelhaft, ob sie wirklich damit zufrieden ist.
|
Dieser Goethe-Roman ist zuletzt Charlottes Geschichte, wie "Der Zauberberg" die Hans Castorps ist. Ihr Charakter ragt hervor, während die Atmosphäre Goethes ziemlich dunkel bleibt, und seine abschließende Äußerung so aussieht, als ob es nur Verteidigung seines Vorgehens wäre. Im Hintergrund dieser Verhältnisse mag sich das ambivalente Gemüt Thomas Manns verstecken. Thomas Mann schätzt Goethe erst noch später in dem Vorwort "Phantasie über Goethe" und in der Rede "Ansprache im Goethejahr 1949" unzweifelhaft hoch und positiv. Man könnte daher sagen, daß die beiden Schriften das Goethebuch Thomas Manns ergänzen, und zwar vollenden.
|
 |
書斎で口述筆記をさせているゲーテ
Goethe diktiert in seinem Arbeitszimmer
aus:
Klaus Schulz
Deutsche Gechichte
und Kultur
Bilder aus 2000 Jahren.
Verlag Langewiesche, Königstein
Max Hueber Verlag, Ismaning.
1972
|
|
|
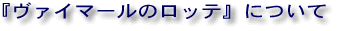
|
|
トーマス・マンはゲーテの最後の恋愛の物語が念頭にあって、巨匠なるがゆえの悲劇を描こうとした、
それは自分の創作に滞りを感じた初老の芸術家が、よわい遅くに生じた「感情」に耽溺してしまい、
ついには破滅をするという筋書にいわば変形して、それが『ヴェニスに死す』という作品になって世に現われた。
それがその後20年の歳月を経て、今度は明らかにゲーテそのものが登場するするというかたちで作品になる。
マンは、老いたゲーテとシャルロッテの面会で、
これがゲーテにとってはきわめて印象の薄いもの、シャルロッテにとっては大いに不満の残るものであったという、
「この両者のわずかな行き違いの感想」に注目したのである。
老ゲーテと婦人との間に見られるわだかまり又は誤解をひとつの物語として描き、その解決を探ってみたいと、
作者はそう思って、この物語に取りかかったようである。
全体がいくぶん喜劇風な筋立てに、なっているけれども、それはあくまで表面上のことである。
作者はゲーテのようなその人生と作品についての膨大な資料のある人物を対象にして、
正面からまともに、深刻に追及しようとすれば、伝記上の諸々の制約を受け、
創作の上で種々の拘束や困難を伴うことを予想し、敢えてそのような雰囲気を醸し出そうとしたのではあろう。
しかしここには芸術家としてのゲーテのその生と作品との関係について核心に触れることが、
当然のことながら、かなりエルンストに扱われている。
物語の中で、ゲーテを取り巻く人たちとの対話を通して、
シャルロッテの内面で意識化されずに漠然としていたものが次第に明瞭な形をとり、
彼女の思想が形成されてゆく。
そしてゲーテ自身はかなりカリカチュアで包まれ、もちろん偉大な作家として描かれてはいるけれども、
その人間性に関して言えば、かなり問題のある人間像と、我々の目に写ることは避け難いことである。
婦人の攻撃の矛先はゲーテの倫理的問題性へと向けられる。
つまり、ゲーテの感情体験は、そのときだけのものに過ぎず、
その行為の責任を十分には負わないままに済ますとすれば、シャルロッテのような立場にある人たちは
単なる犠牲者として甘んじなければならない、
このことは人間の倫理に完全に反する、と彼女は憤慨するのである。
シャルロッテとゲーテは精神的に、そして倫理的に完全に異質の存在であり、
シャルロッテは専ら、人間一般の倫理の側から、ゲーテの精神に対して自己主張をする。
シャルロッテの観劇の後、馬車の中で、ゲーテはシャルロッテに対し
自分の立場を釈明して彼女の了解を求め、シャルロッテは結局はその和解の申出を受け入れるのではあるが、
傍からみれば、シャルロッテは具体的な事例を挙げてゲーテを攻撃しているけれども、
ゲーテの説明は抽象的であったり、比喩的であったりし、十分に意を尽くしたものとは思えない、
少なくともシャルロッテに対する説明としては十分とは言い難い。
彼女が十分にゲーテの説明を理解し納得したのかどうか、それは不明瞭であると見える。
むしろ、こう言えるのではないか、シャルロッテは、「ゲーテのような芸術生活というものが有りえる」
言い換えれば「一個の人間としてよりは芸術家として許容する」気持ちになったと。
彼女の諸々の態度から、彼女はとても思いやりのある、寛容な性質をもった女性であることは
作品の中から十分にうかがえるから。
結局は、この物語はシャルロッテの物語であった、『魔の山』がハンス・カストルプの物語であったように。
従ってシャルロッテの人柄が際立ち、
ゲーテ本人がいくら自分の作品を産み出すその背景を砕いて説明しようとしても、
彼自身の説明では、どうしても、ただ自己の不始末の弁解になってしまうのかもしれない。
あるいは、この背景には、この当時、トーマス・マンのゲーテに対する態度は、
この作品中のゲーテを取り巻く人たちと同じように、
まだ反抗と共感の入り交じったアンヴィバレントなものであったのかもしれない。
これはどうしても、ゲーテの失地回復のためには、
トーニオ・クレーガーの告白のような立場に身を置く作者トーマス・マン自身の口からの
説明、解釈を待たなければならないのであろう。
それと同時にトーマス・マンのゲーテに対する姿勢の変化も必要であった、と言えるかもしれない。
その意味では、シャルロッテの疑問について、作者自身のずっと後年の発言である、
『ゲーテファンタジー』および『ゲーテ生誕記念日に際して』、この二つの評論は明瞭に答えており、
と同時に、トーマス・マン自身のゲーテに対する評価が、少なくともこの時点においては、
紛れもなく積極的なものであり、その価値の認識も揺るぎないものになっていることをよく示している。
そして、いわば、この二つの評論によって初めて、かなり曖昧で、いささかいかがわしいところが残り、
物語の最後までそれを払拭できないままに終わったような印象を与える『ヴァイマルのロッテ』を
十分に補足完成している、とさえ言えるのではあるまいか。 |
|
|
|
|
|
|