
|
|
"Der Zauberberg" ist nicht immer die Geschichte von Hans Castorp, dennoch sagt der Erzähler am Schluß des Romans, es sei zuletzt seine Geschichte. Zeigt das nicht die Neigung des Erzählers zum "unheldischen Helden' und damit sozusagen die tiefe Anteilnahme des Dichters an seinem Ebenbild? Denn zwischen ihnen besteht eine gewisse Ähnlichkeit. Sie zeigt sich, wenn wir das Innere, insbesondere des Gemüt Hans Castorps mit demjenigen seinen Schöpfers vergleichen.
|
Der Dichter hatte die Absicht, durch die geistigen Gegensätze Hans Castorp zu führen. Freilich dem Helden begegnen im Zauberberg verschiedene, merkwürdige Menschen und Ereignisse. Aber es ist zweifelhaft, ob er dort oben menschlich erzogen wird.
|
Hans Castorp keine innere Entwicklung zurücklegt, mit anderen Worten, sich nicht verwandelt. Sein ganzes Leben hindurch ergibt er sich in sein eigenes Schicksal: aus einer Art Pflichtgefühl. Und solch eine Haltung Castorps besteht in der eingeborenen Ordnugsliebe. Seine innere Disposition stellt sich bezeichnenderweise in seinen Begegnungen und Gesprüchen mit Chauchat und Peeperkorn dar. Solche Castorp-Gestalt ist nicht anders als die Reflexion des moralischen Geistes von Th. Mann. Dieser Geist kommt eigentlich von der inneren Dispostion des Dichters her, und der Dichter selbst hätte auch seine Beschaffenheit etwas tadelnswert gefunden.
|
Th. Mann hatte für das Problem der Moral besonderes Interesse. Und er erweitert das Gebiet des Sittlichen, und will das Unsittliche darein einbeziehe. Dabei wäre es aber für den Dichter kein persönliches Problem von reiner Art mehr.
|
|
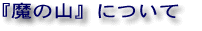
|
|
『魔の山』は、必ずしもハンス・カストルプの物語というわけではないが、
それでも語り手はこの物語の最後に、「結局はきみの物語であった」と言う。
これは「主人公らしくない主人公」にたいする語り手の愛情を示しているのであろう。
それと同時に、作者のいわば自己の分身にたいする深い愛着を示しているのではあるまいか。
じじつ、両者のあいだにはある種の類似性が窺われ、その類似性は、ハンス・カストルプの内面、
とりわけ、その心情を作者のそれと比較してみれば、明らかになる。
|
作者はもともと、精神上の諸々の対立をハンス・カストルプに体験させ、
その体験を通してかれを人間的に形成してゆこうという意図を持っていたようである。
たしかに、この主人公は、『魔の山』で、
多種多様な、一風変わった人間たちに、そして様々な出来事に出会う。
しかしながら、かれが、この山の上で、ほんとうに人間的に教育されたのかどうかは、
きわめて疑わしいところがある。
それどころか、これは憶測だが、ハンス・カストルプは、じつは内的発展を遂げなかった、
端的に言えば、かれの内面は「変化」をしなかったのではあるまいか。
かれはその全生涯を通じて ― 一種の義務感から ― 自分自身の運命に我が身を委ねている。
そしてカストルプのこのような態度は、かれの生来の秩序志向に拠っているようである。
このような内的資質は、かれのショーシャおよびペーペルコルンと出会いの場面に、
なかんずく、かれらとの会話のなかに特徴的に現れている。
要するに、カストルプ像はトーマス・マンの倫理的精神の反映に外ならない。
この倫理的精神なるものは、そもそも、作者の内的資質に由来しており、作者自身、
自分のこのような性質をいくぶん自己批判の気持ちを込めて表現したのであろう。
|
作者トーマス・マンは、モラルの問題にたいして特別な関心を持っていた。
かれは後年、倫理的なものの領域を拡大し、そのなかへ非倫理的なものをも含めようと試みることになるが、
しかしそのときにはもうすでに、この問題が、作者マンにとって、
純粋な意味での個人的な問題とは、もはや言えなくなってしまっているように思われる。 |
|
|
|
|
|