
|
|
| Thomas Mann versucht in der Novelle "Der Tod in Venedig", an die er sich aus Anlaß der Liebe des alten Goethe zu der jungen Ulrike machte, die Problematik der Kunst erneut zu behandeln. Dabei treten der Verdacht gegen das Künstlertum auf als die Kritik an der Hauptfigur, Gustav von Aschenbach, und zwar viel schärfer als in "Tonio Kröger". |
| Aschenbachs innere Probleme, d.h. sein unterdrücktes Gefühl, der Mangel an Menschlichkeit, der Verfall seiner Schaffenskraft usw. deuten an, daß er eigentlich in einem kritischen Zustand ist. Folglich könnte man sagen, daß sein innerer Untergang während seines kurzen Aufenthalts in Venedig Notwendigkeit hat. Aschenbachs Innenwelt liegt in der Mitte dieser Erzählung. Alle Phönomene spiegeln sich in seinen Augen, als ob sie von ihm imaginierte Bilder wären. Und es versteckt sich ein gewisser Selbstbetrug unter seinem Bewußtsein, obwohl er selbst in der Absicht ist, durch die Schönheit das Geistige zu erlangen. An der Stelle des langen Selbstgesprächs von Aschenbach, in dem er den Irrtum seiner Verfolgung der Schönheit gesteht, scheinen die beiden, der Erzähler und die Hauptfigur, innerlich sehr eng verbunden, ja vielleicht heimlich vereinigt zu sein. |
|
|
Die Plan links:
Baedekers Stadtplan zum Reiseführer
Mairs Geographischer Verlag -
Verlag Hallwag A.G.
1987/88
|
|
|
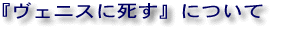
|
|
トーマス・マンは、ゲーテの晩年のウルリーケにたいする愛をきっかけにして、
この『ヴェニスに死す』に取り掛かかった。
そして芸術に内在する諸問題を、改めて明るみに出すことを試みる。
その際の芸術に対する嫌疑や批判は、
『トーニオ・クレーガー』の場合に比して、かなり先鋭化された形で現れている。 |
主人公アッシェンバハに内在している諸問題は、
つまり、かれの感情は抑圧され続けてきたこと、
かれには人間性に欠けるところがあること、
創作力の減退、そして
なかんずく、かれが芸術的に行き詰まっていること、
これらの問題は、かれの内面がそもそも危機的情況にあった、
ということを意味している。
したがって、アッシェンバハが、気晴らしに、ちょっとした旅に出て、
ヴェニスのリードで見掛けた「刺を抜く少年」のようなタッヂオに感動し、
この少年たいする、いたって率直な驚嘆が、
次第次第に、恋慕へ、そして情熱へ、ついには耽溺へ、と変っていった、
この心的崩壊の過程は、ある意味で、必然的な過程であった。
|
この物語は、完全に、アッシェンバハその人を巡って、展開されており、
それどころか、物語の中のあらゆる事象が、まさに、かれの視野の中で、生起している。
そして、なかんずく、かれの内面世界が、この物語の中心に位置している。
かれは、感覚的な人間である芸術家として、
自分は、美を通して、精神的なものへ達しようと努力している、と思い込んでいるが、
残念ながら、ここに、一種の自己欺瞞が潜んでいた。
|
今わの際の夢うつつの状態の中で、ついに、かれは、
これまでの自分の美の追求の仕方に、誤りがあったことを告白する。
つまり、かれの模索あるいは冒険の末にやっとかち得た結論は、否定的なものであった。
しかし、このとき以後、死を間近に控えたかれの様子は、落ち着いていて、
とても冷静になっているように見える。
|
物語の展開の中で、語り手は、しばしば、主人公に対して、批判をし、警告もしてきた。
そのことにより、語り手みずからは、
この耽溺した芸術家とは、意識の上で、かなりの差があることを示してきた。
その語り手が、物語の最後で、この少年愛に溺れた初老の芸術家の死を報告する。
主人公の心の平静に呼応するかのごとく、語り手と主人公は、
内面的に、非常に接近する。
アッシェンバハが芸術家存在について否定的な解答を得たこと、
この芸術家の、いわば死に至る病いは、
のちになって、作者トーマス・マンに新たな問題を提供する。
|
|
|
|
|
|