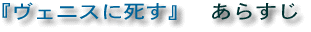
|
|
|
|
ヴェネーツィア、大運河
Aus "Baedekers Allianz Reiseführer, Venedig."
1989, S.118
|
|
|
グスタフ・アッシェンバハは、19 . . 年の春のある午後、
この日の午前中の困難で骨の折れる仕事による興奮から気力を回復させようと、
ミュンヒェンのプリンツレゲンテン街にある自宅から、ひとりでかなり遠くまで散歩にでかける。
5月の初めで、イギリス公園は、まだ若葉が出たばかりだったが、8月のように蒸していた。
しばらくして北墓地の停留所から電車に乗って帰ろうとして、待っているうち、
向こうに見えるビザンチン風な建物の上階の柱廊に男がひとりいるのに気がつく。
その男の容貌は異国風で、鼻が平たく、大きな喉ぼとけで、唇が短く、歯は歯茎までむきだしになっていた。
そのやや異様な風采がアッシェンバハの空想力を奇妙に刺激する。
彼は、湿った、肥沃な、広漠とした熱帯の沼地を思い浮かべる。
不気味な羊歯の茂み、突き出たシュロの幹、不格好なくちばしの不思議な鳥、
そして立て込んだ竹薮のあいだにうずくまる虎の眼が光っている。
彼は自分の心が驚愕と謎めいた渇望のために激しく脈打つのを感ずる。 |
アッシェンバハは、自分の想像力がこのように異様に膨らんだのは、
創作の仕事から、この固定した、冷たい、激しい奉仕を行っている日々の仕事場から
逃れようという衝動の故にであることをよくわかっている。
そしてなぜこのような一種の誘惑がとつぜん現れてきたのかを、つまりその原因は、
自分がこれまで感情を制御し冷却させて、意志の力で精神生活にひたすら励んできたが、
そのような自分の芸術生活そのものの中にあることを、承知している。
彼は、その抑圧された感情がいまや、自分を見捨てることによって、
自分の芸術を、これ以上支えたり生気づけたりすることを拒むことによって、
形態と表現にたいするあらゆる快感を、恍惚を、奪い去ってしまうことによって、
「復讐」をするのであろうか、と考える。
しかしながら、主人公アッシェンバハは自分のこのような危険を孕んだ内的状態を
それほど深刻に受け止めていないどころか、
明確に意識しているのかどうかさえ怪しいところが次第に明らかになる。
一方、語り手は、
この語り手の主人公にたいする態度は、最初からかなり懐疑的かつ批判的なのであるが、
主人公の創作姿勢またその人柄についても種々の問題点があることを指摘し、繰り返し嫌疑をかける。
それどころか、事の顛末をすでに熟知していて、
アッシェンバハのような芸術生活に内在する危険を警告し続ける。
この語り手は、アッシェンバハの外面生活のみならず、内面生活にも極めてよく通じていて、
まるでアッシェンバハの不足した認識を補うかのごとく、彼の意識の奥底へ潜入し、
彼の無意識の心の動きまで顕にする。
語り手が、アッシェンバハという人間の内と外に出たり入ったりするその仕方は、
不思議なほどに自由である。
そしてこの作品においては、語りの部分から主人公の思考や感情の表現へ移行する際に
しばしば体験話法が用いられているが、
その際に語り手と主人公との境界がときおり意図的に不明瞭にされているようにも見え、
それが却って両者の間の推し量りがたい関係あるいは疎通といったものを窺わせる。 |
ともかく、アッシェンバハ自身の意識では、
自分の作品には火のように活動する感情の標識が欠けているような気がして、
それで、夏を少し凌ぎやすい生産的なものにするためには、
ある挿入が、何か即興的な生活、遊惰が、遠い国の空気、新しい血液の供給が必要だ、
という比較的軽い気持ちで、あまり遠くないところへ旅行に行くことを決める。 |
しかし次に、先に挙げたようなアッシェンバハの創作活動が説明され、
続けて、その創作活動にはいかに大きな矛盾が含まれているかが明らかにされる。
語り手は、主人公の内面の秘密を暴露し、さらに彼の創作については、
時とともに、模範的で固定したものへ、洗練された伝統的なもの、形式的なもの、
型にはまったものへと変化して行った、と分析するが、
その本質は「非倫理的であり、反倫理的でさえもあるのではないか」
と非常な懸念を示す。
そしてアッシェンバハが旅に出る前に、彼の芸術生活について、再再度、警告を発する。 |
あの散歩の二週間ほど後には、アッシェンバハは夜行列車でトリエステへ旅立ち、
その翌日ポーラ行きの船に乗る。
イストリア半島の岸辺に近いある島に逗留するが、何か落ち着かない。
突然、自分は本来どこへ行くべきかを悟り、一週間半のちにはヴェネツィア行の船に乗り込む。
そのイタリア国籍の老朽船では、山羊ひげの曲馬団の団長のような顔をした男が、
滑らかなすばしこい動作と空虚な冗舌とで人の心を麻痺させてしまうような振舞で、
アッシェンバハに乗船券を交付する。
船内では、派手ななりをし、ほお紅にかつらの老人がアッシェンバハの目を引く。
下船の際に、この奇態な老人は二つの指先を口にあてたまま、縺れる舌でアッシェンバハに挨拶をする、
と突然、老人の義歯が上顎から外れて、下唇の上へ落ちる。
アッシェンバハがゴンドラに乗り移ると、上向きの短い鼻の、悍しい顔付きをしたゴンドラの船頭は、
小蒸気の発着所までという指示には構わずに、潟を横切ってリードへ向けて漕ぐ。
そして船着き場でアッシェンバハが金を両替している間に消えてしまう。
相変わらず、語り手は、アッシェンバハの心中へ自由に入り込むが、
次第に、アッシェンバハの意識との差を明確にしつつあるようにも見える。
ホテルのロビィで夕食の時間を待っているとき、
ポーランド語を話している家族の中に十四歳ぐらいの髪の長い少年が目にとまる。
その少年の美しさにアッシェンバハは唖然とする。
彼は古代ローマのブロンズの彫像「刺を抜く少年」を思い浮かべる。
翌日の朝食のときも、遅れて入ってきた少年の横顔を見て、それこそ神に近い美しさ、と感嘆する。
アッシェンバハのこのときの感情の発露が、「自然で率直なもの」であったことは間違いない。
|
しかし、午後、小蒸気で潟を横切り、サン・マルコの近くで降りて、町中を散策するが、
狭い街路に淀んでいる蒸し暑さに、胸が締め付けられ、体はほてり、血が頭に上る。
彼は理性的に考え、旅立つことを決意する。
ところがなぜか心は、あるいは感情は、彼の理性的あるいは道徳的な思考に従いたくはない。
翌朝、彼は早くも後悔しはじめ、時間が迫っているのに、必要以上にゆっくりと食事を取る。
乗り合いの汽船に席を占め、船は潟を横切り、サン・マルコを過ぎ、大運河をさかのぼってゆく。
リアルトー橋のみごとなアーチが見えてくるとアッシェンバハの胸は張り裂けんばかりである。
すると駅で手違いが起こる。彼の荷物がまるで方向違いのコモへ向けて送り出されてしまっていた。
それを聞くと、アッシェンバハにはある喜びとおかしさがこみあげ、
腹立たしげな諦めの仮面の下に、不安と自負心とが入り雑じった興奮を隠してホテルへ戻るのである。
その日の昼ごろ、自分の部屋の窓から例の少年タッヂオを見掛けて、
ヴェニスからの別れをあれほどに辛いものにしたのは外でもない
まさしくこの少年のためであったことをはっきりと悟る。 |
アッシェンバハの最初の感嘆は紛れもなく率直なものであったかもしれないが、
以後の彼の少年にたいする感情の変化は、つまり感嘆が恋慕へ、恋慕が情熱へ
そして耽溺へと変ってゆくその変り方は、常軌を逸脱しており、
彼の精神に何らかの異常が生じたのではあるまいか、と思われるほどである。
あるいは、彼の抑圧されていた感情は、かつてのトーニオ・クレーガーのように、
まだ生きてはいたが、目醒めるのが遅すぎたが故に、極端な形を取らざるを得ない、
ということなのだろうか。
それでも彼は、いささか理解しがたいことであるが、
まだ純粋に芸術家として美の対象を観察していると思い込んでいるふしがある。
しかしここには実はある、無意識でありながら、それでいて意図的な自己擬装が施されている。
彼が豊富な知識をもち、古典の思想にも通暁してしているのに、
自己の内面についての省察だけを徹底して怠ってきたというのは、
自己に対する欺瞞以外の何ものでもない。 |
アシェンバハは心の真相を意識の奥に隠して、あるいは強いて意識に上らせないようにして、
自分の感情あるいは思想を正当化しようとする。
しかし疚しい事はしていない、と思っているわけでもない。
アッシェンバハの心的状態にそして彼の精神に目立った変化が現れてくる。
いまや彼の心を領していたのは少年のことだけとなり、彼は予定の休暇の時期が過ぎつつあることに頓着せず、
まるで帰郷の考えは彼の念頭から消え失せてしまったかのようである。
彼の感情は、死に絶えていたわけではないけれども、長いあいだの抑圧で異変を生じたのであろうか、
いまや、奇妙に形を変えて、つまり醜悪に歪んで現れてきた。
無意識の底に潜み、いわば出番を窺っていた感情が委細構わず出現してきた、
あるいは無意識の状態にあったものが、ただ異常な形で意識化されただけなのかもしれない。
それと同時に、彼は、ミュンヒェンの自宅で筆を進めていた労作が一時的に停滞したがゆえに、
創作力を回復し障害を乗り越えようと、ちょっとした旅に出てきたわけであるが、
少年に夢中になったあまり、本来の仕事を放棄している彼のその様子から判断すれば、
彼の芸術的な行き詰まりは、決して一時的なものではなく、
深刻な、場合によっては致命的なものであった可能性がある。
アッシェンバハの理性は崩壊寸前にあり、感情の奔流に巻き込まれつつあった。
彼はタッヂオが旅立つことだけが心配だった。
町なかの薬品のような臭い、貝類に関しての当局の警告の掲示、
そしてドイツ語の新聞だけに載ったあれこれの風評、こういったことを経験したにも拘わらず、
彼は興奮した気持ち、少年の跡をつけ、待ち伏せをした。
|
ホテルの理髪師の美容術の助けを借りて若返ったアッシェンバハは胸をときめかせ、
少年の跡を追って、病んでいる迷宮のような町中へ入ってゆく。
アッシェンバハの精神と肉体はこのころにはもう既に極度に衰弱していたのであろう。
少年を見失ったアッシェンバハは、耐えがたいほどの喉の渇きに苛まれ、
小さな青物屋の店先で、熟しすぎて柔らかくなった苺を買い、歩きながら食べる。
そしてひっそりとした小さな広場の真ん中の水槽の階段に腰を下ろし、
石の壁に頭をもたせたまま、夢想に耽る。
そして自分の教養と思想とそして感情とが交錯した奇妙な一種の自己告白をする。
彼は、冷静に、懺悔の気持ちを吐露する。自分の死が、間近に迫っているのを悟っている風でもある。
この自己告白は、これまでの彼の言動からして、少しく矛盾しているような、
あるいは若干唐突な印象をも受けるのであるが、斟酌して判断をすれば、これは単なる幻想ではなく、
彼が内面的冒険の末に到達したところの思想ということになるであろう。
最後に、語り手が、この初老の芸術家の死を報告するようなかたちで、小説は終る。 |
|
|
|
|
|