|

|
|
Man kann sagen, die "Königliche Hoheit" sei komisch, Märchenhaft und auch oberflächlich. Freilich ist dieses Werk nur scheinbar so gestaltet, denn genau betrachtet, hat es Beziehungen auf das Innere seines Schöpfers, auf Thomas Mann. In diesem Werk ist das Innere als Gemüt und ernsthafte Haltung des Dichters für das Problem der Menschlichkeit miteingeschlossen.
Daher wird hier versucht, nach der Auffassung Th. Manns von der Menschlichkeit zu forschen. |
| Ein einsamer Hilfslehrer, Dr. Überbein, der menschlichemGefühl abgesagt hatte, ging elend zugrunde. Dagegen wurde Klaus Heinrich, der menschliches, naives Gefühl hochgeschätzt hatte, wenn er sich auch dessen am Anfang noch unbewußt war, glücklich. Unter diesem Schluß ist nicht der ironische, sondern der offene Ausdruck des damaligen Gemüts von Th. Mann zu verstehen. |
| Der Held, Klaus Heinrich, ist mittelmäßig begabt, etwas stumpfsinnig, aber er ist gütig, redlich und standhaft. Er ist nicht nur einfältig und naiv, sondern er tut auch voll und ganz seine Pflicht. Kurz gesagt, er erscheint als eine Art idealer Mensch. Solche Klaus-Gestalt hat etwas gemein mit ihrem Schöpfer, aber sie ist nicht der Schöpfer selbst. Diese Gestalt bedeutet vielmehr, daß sich die Sehnsucht und das Ideal, wie der Mensch sein soll, körperlich und als Person, als Klaus Heinrich darstellte. |
| Und hinter dieser Sehnsucht und diesem Ideal könnte sich zugleich Th. Manns Auffassung verbergen, die ursprüngliche Menschlichkeit der Menschen, die sich nun in ungewöhnlichem Zustand befinden, wiederherzustellen. Solch eine moralische Haltung scheint für den Verfasser den Werken von Thomas Mann eigentümlich zu sein. |
|
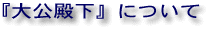
|
|
「トーマス・マンの小説『大公殿下』について、
「この作品は滑稽で、メールヒェン風で、そしてつけ加えれば、浅薄でもある」という意見をもつひとがいる。
たしかにこの作品は、表面上は、そのように見えるかもしれない。
しかしそれは、あくまで「表面上」の話である。
この作品を詳しく観察すれば、かなり、作者の内面との関連をもっている。それが特徴である。
そして、この「作者の内面」は、人間性の問題にたいする作者の心情、
そしてこの問題にたいする作者の真摯な態度として、作品中に、如実に、現れている。
|
寄宿学校の若くて孤独な助教員、ユーバーバイン博士は、
いわゆる「幸福な怠惰」というものとは訣別し、同僚と飲屋のテーブルを囲むこともしない。
「人間的な感情」を断念し、ひたすら仕事に励み続けるが、あるとき、惨めに破滅する。
それに対して、「人間的な素朴な感情」を大切にしたクラウス・ハインリヒは、
(もちろん、この感情を初めから意識していたわけではないが)、最後には、幸福になった。
このような結末は、断じて「イローニッシュ(アイロニカル)な表現」ではない。
この結末は、トーマス・マンの当時の心情の「率直な表出」と理解されねるべきである。
|
主人公クラウス・ハインリヒは、凡庸な才能で、頭がいくぶん鈍いところがある。
しかしかれは、「人間として」は、まさしく「善良で、実直で、かつ毅然として」いる。
それ加えて、かれはただ単に「単純で素朴な」だけではなく、自分の義務は完全に果たす人間でもある。
要するに、クラウスは、一種の「理想的な人間」として表出されているのである。
このような人間像は、むしろ作者の憧憬とか理想が、
つまり素朴な人間への「憧憬」や、人間はいかにあるべきかという「理想」が、
主人公クラウス・ハインリヒの姿を借りて、この小説の中で「具現化されている」、というべきであろう。
|
そして、トーマス・マンのこの憧憬と理想の裡には、同時に、
異常な状態に置かれている人間の、その「本来の人間性」を回復しよう、という決意が込められている。
このような倫理的な態度は、トーマス・マンの諸作品を通じて「特有な」ものである。 |
|
|
|
|
|
|