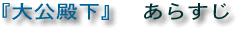
|
これは、芸術家と同様に「象徴的存在という性格を帯びている君主」を主人公にした物語である。
舞台は、フィルヘルム二世時代のある大公国、という設定である。
語り手である年代記編纂者は、淡々と話を進めてゆく。
滑稽さの陰にときおり悲惨さが窺われるが、物語全体の印象としては、概して深刻ではない。
|
クラウス・ハインリヒは、生まれつき「片手が不具」というハンディキャップを背負い、
君主の子という特殊な立場におかれている。
幼い時から、儀礼的・形式的な生活を余儀なくされ、
他の現実的な日常生活を送っている人々との心の交流が許されない。
しかしクラウスは、この「孤独で冷たい世界に」廿んじたくはない。
あるときは、衝動に任せて、皆の実物になる、という苦い体験をし、
そのことで、寄宿学校で知り合った若い助教員ラウール・ユーバーパインに論されもしたが、
それでも、心の触れ合いを求める「人間の本能に根ざした」素朴な感情を抑えることはできない。
そして、莫大な富と、有色人種の血が混っているということで、
クラウス同様、孤独な立場におかれているインマを見かけ、心を動かされてしまうと、
インマに辛辣な言葉を浴びせられ、傷つき、打ちのめされながらも、しやにむに彼女の許に適い統け、
善良な策略家クノーベルスドルフ男爵の助けを借りて、ついにインマとの結婚に漕ぎつける。
|
ところで、主人公クラウス・ハインリヒは幸福を掴むが、
ある事件が、この幸福な結末に一抹の暗い影を落とす。
それは、助教員ユーバーパインが、同僚との些細なもめ事の後、クラウスとインマの婚約の日に、
みすぼらしい自分の部屋でピストル自殺をしてしまったことである。
この自殺は、なかんずく、「それが主人公の幸福と著しい対照をなしている」こと、
そのことに加えて、作者が、後に、『非政治的人間の省察』という作品の中で、次のように述べていること、
つまり「物語の案出者たちは、ある登場人物を破滅させ、他方ある登場人物を幸福にすることによって、
前者にたいしては、個人的な共感を表出し、これと反対に、
後者にたいしては、陽気な軽蔑を表出すること、を好むのである」
このふたつの点から鑑みれば、ユーバーパインの自殺は、見逃すわけにはいかない「重要な事件」である。 |
ユーバーパインは、「白い夫人」の善良で高潔な夫とその子供たちのために、彼女を諦め、
永久に「幸福の怠惰」と訣別し、朝に葉巻を吸う暇のある連中を軽蔑し、
同僚と飲屋のテーブルを囲むこともなく、ぎりぎりの限界まで精神を緊張させ、
業績を挙げるべく、ただひたすら仕事に励んできた。
「それほどまでに努力したのにも拘わらず、躓いた」ということが、ユーバーパインに大きな衝撃を与え、
彼を自殺へと追いやったのであろうか。
しかし、これだけでは釈然としない。
「ロマンティッシュな個人主義著ラウール・ユーバーパインは、極めて底意のある仕方で惨めに破滅する」
と作者自身も、後に発言していることではあるが、
ユーバーパインが、当てつけがましく若き二人の「婚約の日」に自殺をしたということは、
些細なことがきっかけとなっているにもせよ、
クラウスに対する「絶望」が最大の要因であったことを暗示している。
|
クラウスは「バロメータの水銀は低気圧のときに下がるのです。高気圧のときにではありません、殿下」
とインマに言われて当惑したり、詩人マルティーニとの会見の折には、その話がよく呑みこめない。
しかし、クラウスは「人間」として、芯のある、しかも素朴で、自分の感情に忠実である。
妹に、詩人との会見後、こう断言する。
「かの詩人と知り合いになったことを喜べるのかどうかわからない。彼はどこか恐ろしいものをもっている」と。
|
哀れな最期を遂げたユーパーバインについてみれば、
ほとんど意見らしい意見を扶まない物語の語り手をして、
「人生は職業と業績とに帰するのではない。人生はその純粋に人間的なもろもろの要求と義務とをもっている。
これらに注意を払わないということは、仕事の領域での自分および他人にたいする陽気さより以上に
重い罪を意味する。」と言わしめている。
|
全体としてみれば、たしかに、この物語のもつ雰囲気は明るく、また滑稽でもある。
しかしその明るさ、滑稽さの中から、ときおり、「暗さ、悲惨さ」が陰画として浮かび上がってくる。
クラウスにも、破滅の恐れが全然なかったわけではない。
生まれながらの不運、取り巻かれた状況、苦い体験、
これらには「デカダンスや悲惨」に通していく危険がじゆうぶんに含まれていた。
滑稽さの陰に悲惨をも感じさせるヨハン・アルブレヒトの最期とドロテーアの晩年、
そして「もしも古城でずっと過ごしていたなら、私は耐えられず、
かわいそうなママのように頭が混乱し、奇妙になってしまったでしよう」
というティトリンデの言葉がそれを暗示している。
しかし、これは作者が附与したわけであるが、いささか鈍感で、人間としては平凡であるが、誠実であり、
しかも敢然と事に当たる、というクラウスの素朴な人間性がその危険を踏みこたえた、と言える。
|
クラウスとインマは、クノーベルスドルフの手助けによって、ひとまず幸福になった。
二人は現実の問題に取り組んでいこうとする。
しかしインマは、自分たちが人間的な生活を送ることができるのかどうか、
自分たちに人間らしく生きる能力があるのかどうかに、まだ不安をもっている。
「私たちは、ユーバーバイン博±がいつも言っていたということですが、人々の上に立っていながら、
愚かで、かつ孤独です。そして生活についてはまるでわかっていません!」
たしかに、これには疑問が残る。
二人はこれから後も、あの頭のぽけた年金生活著フィンメルゴットリドプのように、
ただ役にも立たない「合図をする」だけのことになるかもしれない。
しかしクラウスには希望がある。
「愛というものを知っている者が、生活というものを全然知らないのか?
これが今後のわれわれの問題だ ― つまり高貴と愛の両方 ― 厳しい幸福が。」
クラウスの言葉には、人間らしい生き方を求める気持と同時に、生ぬるい幸福に溺れまいとする倫理的態度
― これはユーバーバインの教えを汲み取っていることを示すのであろう ― が窺われる。
|
作者トーマス・マン自身、結婚して、まだ間もないころに、
友人のヴィトコプ宛に、次のように書き送っている。
「良心も安らぎません。というのは事実≫幸福≪にたいする私の恐れが小さくないからです。
そして私は、なお依然として、≫生≪への私の献身がそもそも高度に道徳的なものであるのか、
それとも一種の自墜落であるのか、と疑っています。」
このように、結婚のほとぽりが冷めるか冷めないうちに、たとえそれが道義的な観点からであるにもせよ、
もう獲ち得た幸福に疑念を懐いてしまうような人が、
クラウスのように「厳しい幸福」で簡単に納得するとは思われない。
トーマス・マンは、後に『略伝』(1930年)において、
「このロマーンの形をとった喜劇の試み、これは同時に≫幸福《との契約の試みをも意図した」
ということをも言う。
|
ただ、「今回もまた、自分の生活について物語った」というトーマス・マンの当時の発言、更には、
「姿勢を崩さず、表情を変えず、片足で立ち続け、しかし内には、じつに優しい心をもっている玩具の兵隊」
クラウスが、種々の点で、よく類似している『玩具の兵隊』(アンデルセン)について、
このメールヒェンがとりわけ好きで、しかも自分の「人生の象徴」とまで、表現していることなど、
を考慮すると、こう言えると思う。
クラウスの人間像は、作者トーマス・マンが自分のことを象徴化し、
さらにそこヘ、かれの「憧憬」が、この言葉はマンがもっとも愛している言葉のようであるが、
この「憧れ」が反映され、理想化されたものである、と。
「単純素朴で実直な人間」、こういう人物には、もう今さらなることができるわけではないが、
求めてやまない永遠の「憧憬」であって、その憧憬の対象に形を与え、
ひとりの理想的人物として表わしたのではなかったか、と。
|
ついでに、単純で素朴ということに限っていえば、これがもっともよく現れているのは、
傷つきやすい性質ではあるが、実業家になった陪臣男爵と結婚し、王女の地位を捨て、市民の生活に入り、
はじめは部屋じゅう植木鉢や花台でいっばいにし、子供が生まれると、今度はそれに夢中になるという、
平凡ながら幸福な生活を送っている無邪気なデイトリンデである。
デイトリンデは、理窟ぬきに好感がもてる。 |
 |
Ein Teil von der Abbildung,
aus:
"Der standhafte Zinnsoldat"
in:
Die Schönsten Märchen
von
Hans Christian Andersen,
Spectrum-Verlag,
Salzburg, 1969
|
|
『大公殿下』の主人公、クラウス・ハインリヒは、
アンデルセンの童話『毅然とした錫の兵士』の主人公、すなわち:
姿勢を崩さず、表情を変えず、片足で立ち続け、しかし内には優しい心をもった玩具の兵士に、
種々の点できわめて類似している。
トーマス・マンは晩年に、ある友人宛に:
「私はいつもアンデルセンの『毅然とした錫の兵士』をとりわけ好んでいました。
このメールヒェンはじつは私の人生の象徴なのです。」
と書いた。
|
|
|
|
|
|
|