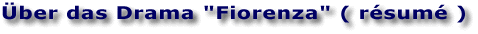
|
|
Der Held dieses Dramas ist Girolamo Savonarola, der Prior von San Marco, und der Höhepunkt des Dramas ist die Begegnung zwischen dem Prior und Lorenzo de' Medici, dem Renaissance-Fürst, am letzten Auftritt.
|
Thomas Mann sagt später von Savonarola: "seinem Leben galt der größte Teil meiner Vorstudien, seinem Charakter meine intimste psychologische Teilnahme". Aber der Dichter hat seine Erfahrung in solche Savonarola-Gestalt kaum übertragen. Freilich können wir einige Verhältnisse zwischen ihnen vermuten: in der Savonarola-Gestalt ist der Wunsch des Dichters, seine Schwäche zu überwinden, miteingeschlossen; der gründlich ethische, asketische Geist des Priors ist wohl ein Ausdruck der Selbstkritik des Dichters. Savonarola enthüllt aber den inneren Widerspruch bei der Auseinandersetzung mit Lorenzo, und es zeigt sich, daß er eine äußerst beschränkte Person ist, obwohl er als großer Geistesmensch am Kampf den Sieg gewinnt.
|
| Thomas Mann verkörperte "eisige Geistigkeit und verzehrende Sinnenglut". Er stellte dieses beiden Extreme gegeneinander, trotzdem das für ihn selbst kein persönliches, wichtiges Problem ist. Und dabei veränderte sich seine Anteilnahme an Savonarola, dem asketischen Idealisten,, wahrscheinlich nach und nach, während er das Drama schrieb. Offen gesagt, er scheint immer deutlicher erkannt zu haben, daァ dieser Held für ihn wesentlich ein fremdartiges Dasein ist. |
Im Vergleich mit seinem Gegner Savonarola ist Lorenzo de' Medici menschlich und anziehend dargestellt. Der Dichter hatte wohl als Lebensbejaher unwillkürlich Sympathien für Lorenzo, und so ist diesem die Seele des Dichters ein wenig eingegeben worden.
|
|

|
|
この戯曲の主人公は、サン・マルコ修道院院長ジローラモ・サヴォナローラであり、
他の登場人物たちの会話はすべて、この修道院長のことに集中し、
最終の場におけるこの修道院長とロレンツォ・デ・メーディチとの対決に至るまでの、長い前奏曲となっている。
そしてなかんずく、院長を際立たせるための役割を果たしている。 |
作者は、サヴォナローラについて、資料を研究し、かれの足跡を辿り、
『フィオレンツァ』のための習作とも言うべき『神の剣』をも書いていた。
「予備的研究の大部分をサヴォナローラの生涯に向け」、
この人物に対しては、内心「きわめて深い心理的関心を寄せていた」という。
しかし、もしもそうであったならば、作者トーマス・マンの性格や感情や思想が、
本来であれば、大いにサヴォナローラに投影されてしかるべきであった。 |
ところが、実際に作品中にあらわれた「サヴォナローラ像」は、純粋精神の担い手、偉大な精神の人として、
たしかに、ロレンツォとの対決において、事実上の勝利を収めはするが、
しかし、同時に、ロレンツォとの対決の中で、次第に内面の分裂と矛盾を露呈し、
そしてまた、サヴォナローラかれ自身が、きわめて「偏狭な人間」であることが、次第に明らかになってゆく。
それゆえ作者の内面は、サヴォナローラへ、少なくとも直接的には、投影されなかった、と思われる。
|
「サヴォナローラへの強い関心」という作者の言、それは、「共感」とは別物なのであろう。
この表出に含まれている「意味」は、つまりは、傷つきやすい性質、繊細さをもっていた作者自身が、
これらの弱さを克服した「英雄精神」に、一種の願望を抱いていたこと、
そして、作者は、「生への献身」というものに、ときどき疑いを抱き、
それゆえにこそ、この修道士の徹底的に倫理的な精神を、
いわば「自分にたいする戒め」にしたいという気持ちがあった、ということではないのか。
そして、けっきょく、戯曲中のサヴォナローラ像が、「偏執狂的性格をもった人間」として描かれたのは、
「人生の肯定者」たる作者トーマス・マンとして、
「生」を拒否した純粋精神なるものには、「限界」を感じたゆえにであろうか。 |
なぜかかる事態が生じたのであろうか。
人間性というものに付きまとわれている作者が、精神性と官能という、
ともに人間的なものに対立するものを強引に具象化し、対峙させようとした。
これがこの作品の失敗した原因であり、作品発表後の作者の発言が分裂している原因でもあると思われるが、
そのために作者の個人的な枠の外での展開になってしまった。
そして生の肯定者で、「人間性がその本性に深くかかわっている」作者の関心は
構想を固めてゆくうちに、あるいは執筆中に、すこしずつ変化をし、
主人公である精神性の代表者、禁欲的な理想主義者サヴォナローラが、次第次第に、作者自身から遊離し、
この精神的離反が、まさしく、作中のサヴォナローラ像に「影響」を及ぼしたのであろう。
他方、生の肯定者である作者の共感は、なかば無意識のうちに、
生との関わりが深い、官能芸術の代表者ロレンツォに好意を抱くようになり、
その結果、作者の「魂」が、かろうじてではあるが、ロレンツォに吹き込まれ、
かれにいくぶんなりとも「人間性」を付与することになったのではあるまいか。 |
 |
ロレンツォ・デ・メーディチ
Aus:
"Baedekers Reiseführer, Florenz."
Karl Baedeker Verlag, 1989
|
|
|
|
|
|
|