
|
|
| Der Roman "Buddenbrooks" ist die Geschichte einer Familie, deren feste bürgerliche Grundlage nach und nach zerfällt. Und mit dem Niedergang dieses Geschlechtes verbindet sich der Keim der Kunst untrennbar. Ein symbolischer Ausdruck desselben ist eben Hanno Buddenbrook, der in der Jugend an Typhus stirbt. |
Wir könnten wohl sagen, daß Hanno Buddenbrook am Leben bliebe, und in der Novelle "Tonio Kröger" als ein empfindlicher, träumerischer und einsamer Junge aufträte.
|
| Daher ist hier nötig, dem gang der Handlung folgend, den inneren Konflikt von Tonio Kröger, dem Helden dieser Novelle, deutlich zu machen, und dann die Bedeutung des Schlusses, zu dem Tonio kommt, sowie die Beziehungen auf das Innere seines Schöpfers, zu erforschen. |
Tonio Kröger ist ein Entfremdeter in der bürgerlichen Gesellschaft. Trotzdem kann er sich in die Welt von Kunst und Geist nicht einschließen, weil er am Ende menschlichem Gefühl nicht absagen kann. Während seines einstigen ausschweifenden Lebens litt er nicht wenig. Er hat seiner Freundin Lisaweta Iwanowna seine Gewissensbisse und die Sehnsucht nach naiven Menschen gestanden, infolgedessen wird er von ihr als "ein Bürger auf Irrwegen" erledigt. Aber für ihn gibt es eigentlich keinen anderen richtigen Weg. Er verreist nach Dänemark. Dort in einem kleinen Seebad bekennt er sich zur Charakterrisierung als "ein Bürger, der sich in die Kunst verirrt, ein Bohemien mit Heimweh nach der guten Kinderstube", und er entschließt sich, in der Mitte zwischen Geist und Leben, Künstrertum und Bürgerlichkeit niederzulasen.
|
| Am Schluß der Novelle, d.h. im Brief an seine Freundin äußert Tonio Kröger folgenden Wunsch: Er wolle, indem er sich zwischen zwei Welten stelle, die Armen und Leidenden erlösen, und die Liebe zum Menschlichen, Lebendigen und Gewöhnlichen pflegen, wenn es auch unerwiderte Liebe sei. Aber diese Erlösung heißt vermutlich, nicht nur die armen Leute, sondern auch sich selbst zu erlösen, weil seine Vergangenheit eben "tragisch und lächerlich" war. |
| Wir können in Tonios Herkunft und Handeln manche Ähnlichkeiten in Thomas Manns Leben finden. Was die Gem殳sverfassung und den Gedanken betrifft, so ist es sogar nicht leicht, den Helden von seinem Schöpfer zu unterscheiden. Daher denkt der Verfasser, Tonios innerer Widerstreit sei für den Dichter selbst, der als Künstler den künftigen Weg sucht, eine wichtige und dringende Problematik gewesen, und der Dichter habe mit dem Schluß, zu dem Tonio kommt, eine innere Krise überwunden und sich von seinem Zwiespalt gelöst. Diese Novelle wäre also ein Wendepunkt in der Lebensgeschichte des Dichters. |

|
古リューベック
Aus Abb. von: "Baedekers Stadtführer, Lübeck." Karl Baedeker GmbH,1989
|
|
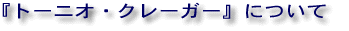
|
|
長編小説『ブデンブローク家の人びと』は、
その堅実な市民生活の基盤が徐々に崩壊してゆく、ある家族の物語であった。
そしてこの一族の没落と芸術の胚胎とが不可分に結び付けられていた。
チフス罹って夭折するハンノ・ブデンブロークは、まさにその象徴的な表出に外ならない。
このハンノ・ブデンブロークが、生きながらえて、あるいは、復活をして、
感受性の強い夢想的な少年として『短編少年トーニオ・クレーガー』に登場する、
という表現が、もしや許されるかもしれない。
この少年は孤独に悩み、自己の存在を意識し、と同時に、それに疑いを抱きながら、
次第に芸術家へと形成されてゆく。
それゆえ、ここでは、主人公トーニオ・クレーガーの内的葛藤を明らかにし、
さらに、トーニオが到った結論の意味、ならびに、それがもつ作者トーマス・マンの内面との関連を
探ってみたい。 |
トーニオ・クレーガーは、市民社会のなかでは、いわば異邦人であるが、
それにも拘わらず、芸術と精神の世界だけに閉じこもることはできない。
なぜならば、かれはどうしても、「人間的な感情」を断念できないからである。
かつては、放蕩な生活に耽ったことがあったが、ただ苦しみを嘗めただけであった。
あるとき、かれは女友だちのリザヴェータ・イヴァーノヴナに、
自分の良心の呵責と素朴な人間への憧憬を打ち明ける。
しかしその結果、かの女に、いともかんたんに、あなたは「道に迷った市民」にすぎない、
と片付けられてしまう。
しかしながら、かれ自身にとっては、他の「ふさわしい道」などは、そもそも存在しなかったのである。 |
かれは旅に出て、デンマークへと向かう。
そこの、とある小さな海水浴場に逗留しているうちに、
かれは、自分がまさしく、「芸術に迷い込んだ市民、良き子供部屋への郷愁を抱いているボヘミアン」
であることを容認する。
そして、「精神と生」とのあいだ、「芸術家気質と市民性」のその中間地点に、居を定めることを決意する。
有り体に言えば、宙ぶらりんのまま、それで良し、とするのである。
|
この短編小説の結びの部分で、つまり女友だちに宛てた手紙のなかで、
トーニオ・クレーガーは、みずからの到達した結論を述べる。
かれは、自分は二つの世界のあいだに立って、哀れな人びと、苦しんでいる人びとを救済し、
そして人間的なもの、活き活きとしたもの、そしてありふれたものにたいする愛を、
たとえそれが報いられることのない愛であっても、育んでゆくつもりである、
という意味の結論、あるいは願望を表明する。
しかしこの救済とは、じつは、単に、哀れな人びとを助けるというばかりではなく、
自分自身をも救うことを意味している、と思われる。
なぜならば、かれの過去の体験がまさしく「非劇的で、かつ滑稽な」ものであったからである。 |
そして、この報われることのない愛を育むというところは、
トーマス・マンの感情を率直に表出したものではなさそうである。
というのも、当時かれの心の中では、じつは諦めの気持ちと願望とが交錯していた節がある。
そのことは、かれの当時の書簡などからも読み取れる。
言ってみれば、「感傷的なナルシシズム」でもって自分の心の平静を得ようとしたのではないか。
このトーニオ・クレーガーの愛というものは、むしろ、「作者の孤独な心的状態の反映」
と解釈すべきではなかろうか。
主人公の素性およびその行動の軌跡は、
作者トーマス・マンのそれと随所で重なり合うというばかりではない。
それどころかその心理と思考に関して言えば、
主人公と作者のあいだには距離がほとんどなくなってさえいる。
従って、トーニオの内的葛藤は、芸術家としての将来の道を模索していた作者自身にとっても、
重要で切実な問題だったのであり、作者は、トーニオが到った結論によって自分の内面の危機を克服し、
自己分裂を免れた、ととも言えよう。
それゆえこの自伝的作品は、作者の生涯における一転機を画すものである。 |
|
|
|
|
|