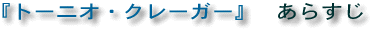
|
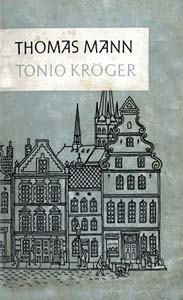
|
左図は、学生用廉価版
『トーニオ・クレーガー』の表紙
Abbildung links: der Umschlag von:
Thomas Mann, Tonio Kröger,
S. Fischer Schulausgaben,
S. Fischer Verlag, Berlin,1966
|
|
|
北ドイツのある小さな港町を背景にして、物語は始まる。
トーニオ・クレーガーは、穀物商会を営み、町で勢力をもっているクレーガー領事の息子で、
このとき十四歳であった。
学校では、教師の話にはまるで耳を傾けず、
もっぱら、友達との交際で嘗めた苦渋を、いちずに思いつめることに没頭し、
家に帰れば、読書に耽り、詩のようなものを書く。
そのような少年であった。 |
学友に、ハンス・ハンセンという、活発で、しかも容姿端麗な優等生がいて、
トーニオはとても好いている。
しかしハンスは、悪気はないのだが、待ち合わせの約束を、つい忘れてしまうし、
トーニオが『ドン・カルロス』から受けた感動を、熱心に語って聞かせようとしても、
ハンスは、そのような話には、じつは余り気乗りがしない。
かれは馬のスナップ写真などの方が、はるかに面白いと思っているのである。 |
十六歳になったトーニオは、金髪で、切れ長の青い眼をした少女に心を奪われる。
インゲボルク・ホルムという名のこの少女にたいする気持は、
以前ハンスにたいして懐いた感情よりも、はるかに強いものであった。
それで、かつての経験から「愛は自分に幾多の苦痛と圧迫と恥辱とをもたらすに違いない」ことを
すでに学び取っていたにも拘わらず、進んでこの愛に身を委ねる。 |
ところが、ある時、ダンスの講習会で、インゲと同じ組になったトーニオは、すっかり狼狽し、
まちがえて、女の子たちの中へ紛れ込んでしまう。
それで、ダンス教師のクナークに揶揄され、その場の一同の笑いものとなる。
トーニオはその場所からそっと抜け出して、閉じた鎧戸の前に立ち、
まるで外が見える風を装って、インゲが慰めに来てくれるのを、ひそかに待つ。
しかし、そのような事は起こるはずかなかった。 |
トーニオもそれを悟ったが、それでも、
つまり相手に届かない妄想的な愛であっても、そこに幸福を見出そうとする。
そして、インゲにたいするこの気持を、誠意をもって護ってゆくことを心に誓う。
しかしながらこの愛の焔は、時日の経つうちに、その勢いが次第に弱まり、
かれは手を尽して煽ったのだか、遂には、ひっそりと消えてしまった。
トーニオは、自分にはあるものと思っていた「誠実」が、まるで当てにならないものであったことを知り、
悄然とし、また、すっかり幻滅して、冷え切った心で、わが道を進んで行く。
つまり、芸術の分野で自分なりの仕事をする気概と力量を内に感じ、
それを為遂げるために、いわゆる人間的な感情を儀牲に附したのである。
|
|
そうこうするうちに父が亡くなり、商会は解散し、
衝動的で自堕落な母親は、ある音楽家とどこかへ行ってしまった。
かくしてトーニオは故郷を去ることになる。
かれはもはや何らの苦痛を覚えることなく、精神と言葉だけの荒蓼とした世界に身を投ずる。
愛と誠実とを失った今、無節操な生活に陥り、淫蕩に耽った。
そして健康を損ないながらも、こと天職に関しては、徹底性と勤勉とでもって励んだ。
このような「氷のように冷たい精神性と身を焦がす官能の灼熱」との両極を往き来しつつ、
トーニオは良心の呵責に苛まれる。 |
三十歳を少し越したトーニオ・クレーガーは、
友人のリザヴェータ・イヴァーノヴナのアトリエに姿を現わし、芸術についての見解を述べる。
それは要するに、芸術家であろうとすれば人間的な感情を捨てなければならない、というものである。
しかしかれは、このような意見を吐きながら、みずからは、それに徹しきれない。
かれには、神経が過敏になる春を軽蔑して、この季節にカフェーに逃避する、といったことはできない。
そういう行為は、かれにとっては、後めたいことなのである。 |
トーニオ・クレーガーは幼い頃から感受性が強く、自己の体験をよく心に留めて、熟考を重ね、
そこから詩や思想を創り出す才能を身に具えてはいた。
しかし性格は懐疑的で、心の内では絶えず煩悶が繰り返されている。
かれは、自分は純粋な詩人ではない、したがって
享受するに値する豊かな内面を付与されてはいない、と自己分析をしている。
そして、自分は「知るために生まれてきたのではないのに」
宿命として、そのような状態におかれた、という意識をもっている。
従って、かれに言わせれば、かれにとっての文学は、決して天職どころではなく、
まさに「呪い」である、ということになる。
それゆえ、かれは、「飽くなき美の追求」に対しては、疑念を持つ。
次の発言は、そのようなトーニオの心情をよく表わしている。
「感情の涙のヴュールを通してまでも透視し、認識し、記憶し、観察して、
その観察したものを、互いの手が絡み合い、唇が触れる瞬間、
人間のまなざしが感覚によって曇らされ見えなくなる瞬間においてもなお、
微笑しながら取っておかなければならない、一 これは恥ずべきことです、
リザヴェータさん、卑劣で腹の立つことです....」 |
そしてかれは、話の最後に、じつは「私は生を愛している、一 これはひとつの告白です。
一 今まで誰にも打ち明けたことはない。」
しかもその生とは、ニ一チエの唱えるチェーザレ・ボルジアなどの生とは異り、
もっと無邪気で素朴な生のことであり、
自分の憧憬の対象は、まさに、かつてのハンスやインゲのような人びとである、と言う。 |
この告白の結果、リザヴェータによって、「あなたは道に迷っている市民です。」
と一言のもとに片づけられる。
トーニオは少し怯み、しばしの沈黙ののち、慇懃に立ち去って行く。 |
|
すでに三十歳を少し越したトーニオ・クレーガーは、これから辿る道を決めなければならない。
だがかれは、今後の方向を、おぽろげながらも見定めつつあったようである。
トーニオ・クレーガーは、旅に出ることを決意する。
道筋は、途中で、みずからの「出発点」に触れながら、デンマークへ向かうというのであった。 |
「トーニオは北へ向かった。」
「かれは自分の出身地てある狭い町の尖塔が灰色の空に賛えるまで休まなかった。」
しかし、故郷の町に降り立ち、以前の住居を訪ねると、いまはもう、見知らぬ他人が住んでいた。
かれは、自分がすでに疎遠な存在になっていることを知る。
これでもう用は済んだ。 |
|
トーニオは荷物をまとめ、再び北へと向かう。
船でコペンハーゲンに上陸してから、更に北上し、
「最後のそして本来の自標」であるオールスゴーに逗留する。
この静かな海辺で、一 かれ自身心の隅ではひそかに期待していたと恩われるのだが、一
かつて少なからず心を動かされたインゲボルク・ホルムとハンス・ハンセンとに、
その雰囲気がとてもよく似ている二人連れに遭遇する。 |
トーニオは、なぜ自分の「出発点」に触れながら、この北国へとやって来たのであろうか。
もちろん今更,昔の二人と同類の人間を捜し求めて、ただ感傷に耽る、というだけではない。
しかし、何か新たな解答を、あるいは、全く未知のものを捜しにやって来た、というのではない。
「最後のそして本来の目標」と述べられている通り、かれの心中には、既に、ある予感が生じていたのであり、
前方に見えつつあった今後の道を確認し,気持を固めるための旅であったのだろう。
そのためには、例の二人連れが、背景として、必要であった。 |
|
|
|
|
|